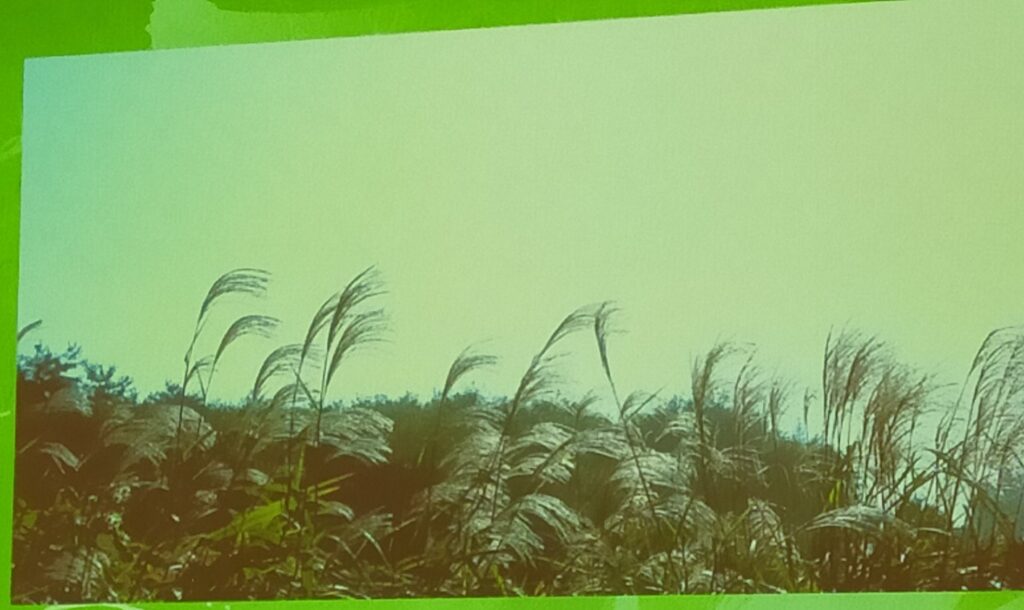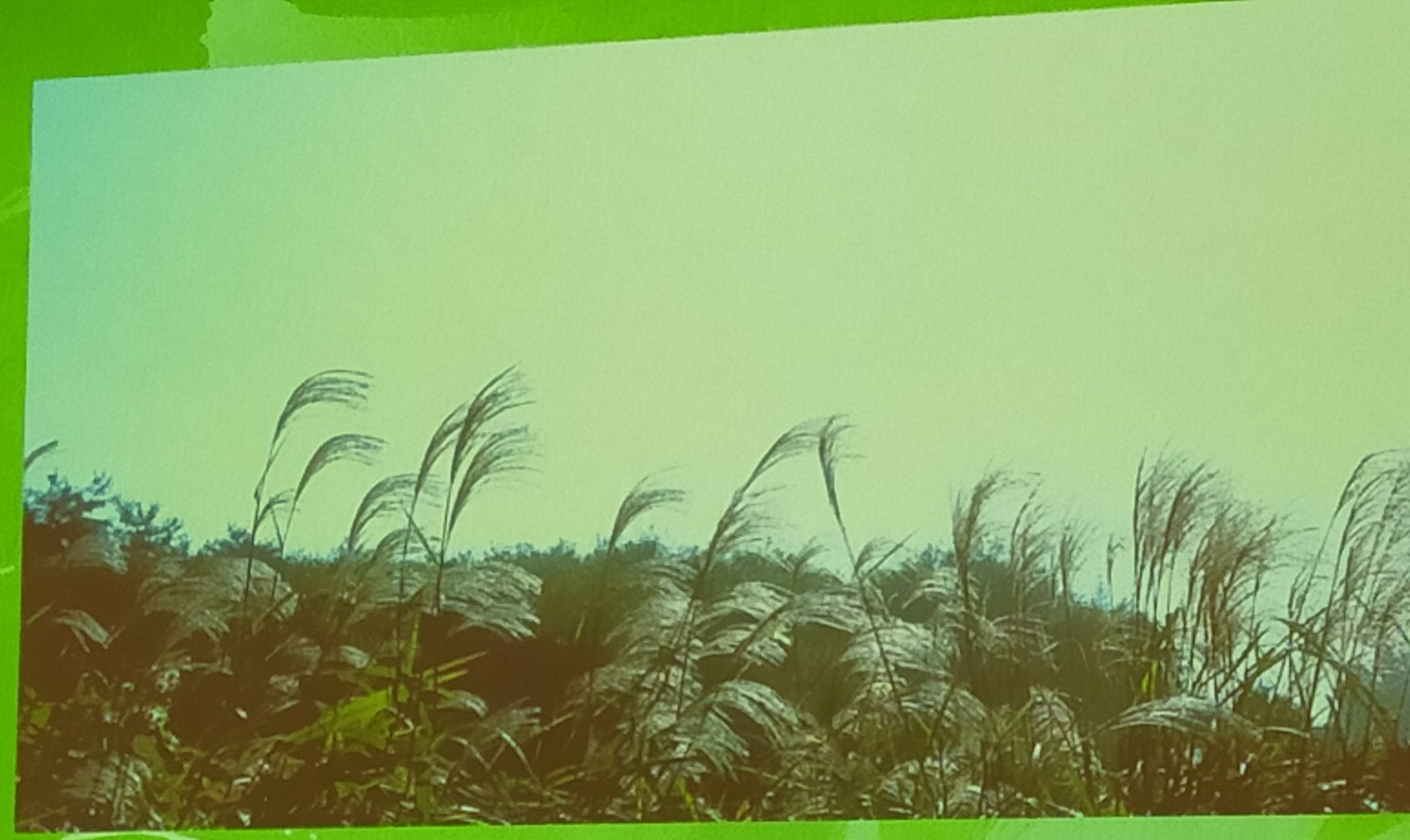富士見市で宮瀧交二大東文化大学教授の「東上線沿線の都市の形成」と題する講演を聴いた。興味深かったのは、武蔵野は昔はすすきの原だったという話である。今の武蔵野と言えば雑木林の風景が思い浮かぶが、少なくとも江戸初期の17世紀半ばまでは見渡す限り一面のすすきの原だったという。それが雑木林になったきっかけは、明暦元年(1655)の野火止用水の完成で、それ以降畑作が可能になり、堆肥や燃料を得るためにナラ、クヌギなど雑木が植えられた。武蔵野は畑と雑木林となった。ところが、不思議なことに雑木林の時代に描かれた武蔵野の絵画もすすきの原の風景が多い。全国の美術館にある「武蔵野図」もすすきの原に春秋の七草、富士山などが描かれている。つまり、国木田独歩「武蔵野」から雑木林を美しいとの見方が広がったが、それ以前もそれ以降も、人々は今は見られないすすきの原の風景を美しいと思い、なつかしんでいた。それだけ武蔵野のすすきの原は趣きのある風景だったのである。